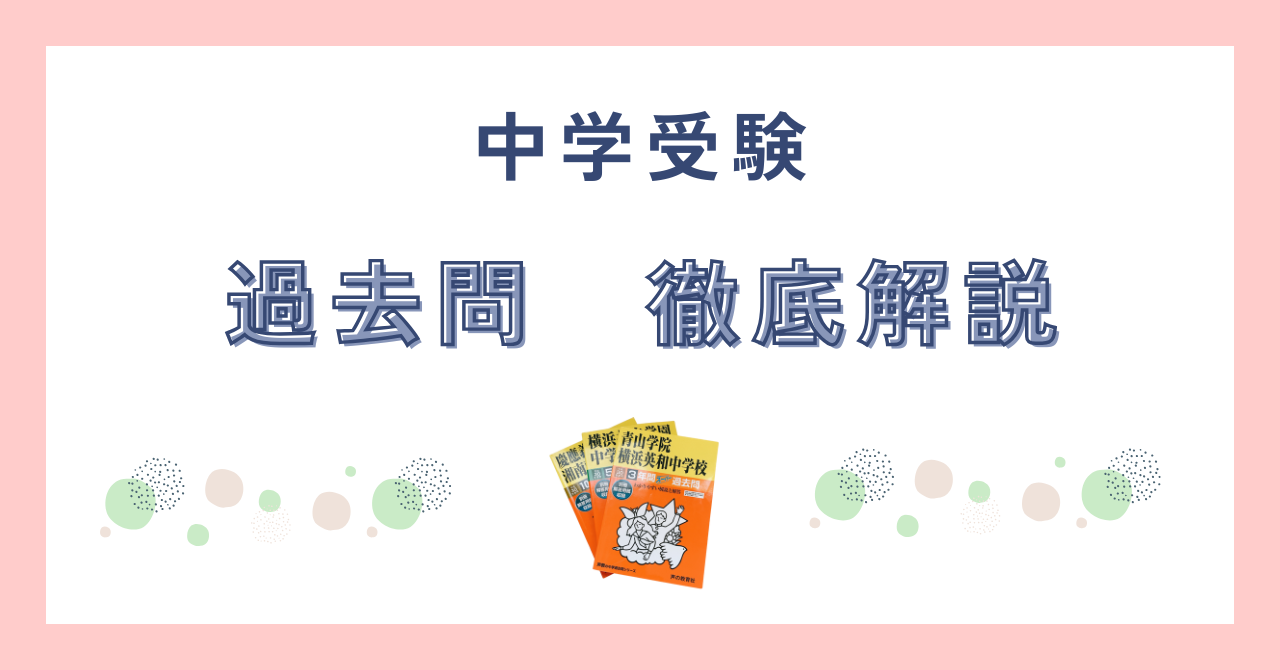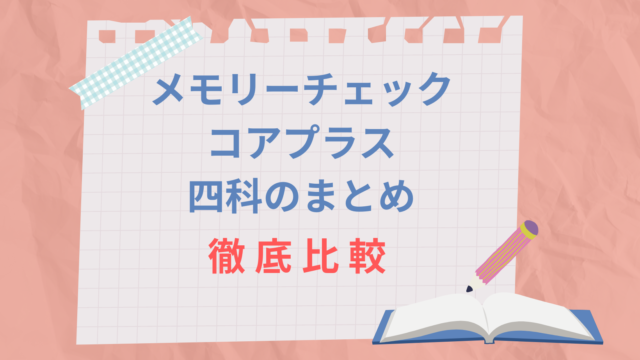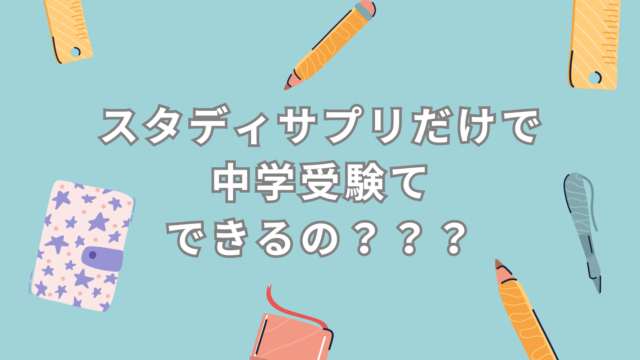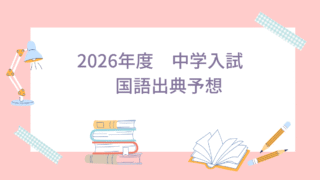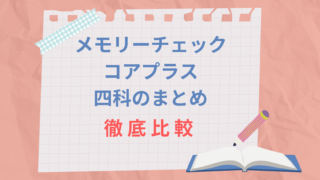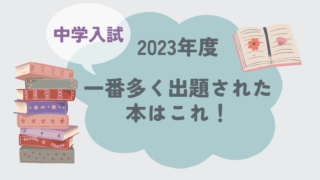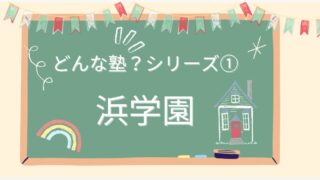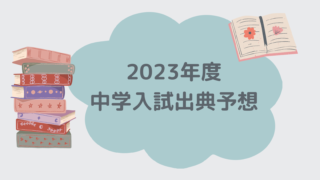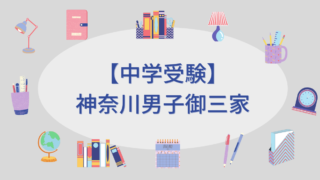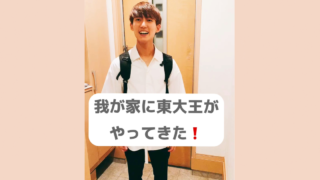夏休みが終わって、ホッとしたのも束の間、6年生はいよいよ過去問の季節ですね!
私は普段インスタグラムで月に2回ご質問を受け付けているのですが、この時期になると急に増える質問が、過去問について、です。
そして、私自身も3回の中学受験を通して、一番試行錯誤したのが、この過去問対策。
過去問については、色々な先生や有識者が、様々な持論を展開されていて、
「一体どれが正解なの~!!!」となっているママも多いと思います。
例えば、過去問は新しいほうからやるのがいいのか、古いほうからやるのがいいのか・・・、というテーマにおいては、入試の傾向は変わるから、あまり古いものをやっても意味がない!新しいほうからやるべき、というかたもいれば、新しいものを早々にやってしまっては、入試が近づき実力がついてきて、ようやく合格の可能性を図れる、って時に古い過去問しか残っていないということになりかねない!という意見もあります。
なので、まず最初にお伝えしたいのは、過去問の取り組み方に
「これが万人にあてはまる絶対的な正解!」っていうものはないということです。
どんな学校を何校受けるのか、やお子さんの性格によっても違う。 ママ友に「うちはこんな風にして取り組んで合格したよ」って言われても、それがそのままお子さんに当てはまるとは限らないんです。
そこで今回は3回の中学受験と家庭教師として生徒さんと向き合う中で見つけた私なりの答えと、その根拠そして、皆さんがどんな基準で選択していけば良いのか、をお伝えしたいと思います。
塾によっても先生によってもおっしゃることは違います、ご自身の納得感がある方法を選んでいけばいいんです、それがそのご家庭にとっての「過去問の最適解」になるはずです!
はじめに
まず初めに、過去問はなぜやるのでしょうか?
そもそもやらなければいけないものなのでしょうか??
このなぜ過去問をやるのか、がわかっていれば、この先何年分やればいいのか、どの学校からやればいいのか?順番は?など迷ったときに、選ぶべき道が見えてくると思います。
過去問をやる意味はざっと次の5つに分けられると思います。
1. その学校が「求める力」を知ること
各学校は独自の教育方針に基づいて問題を作成しています。
過去問を解くことで‥
- どんな学力を重視しているか
- 基礎重視なのか応用重視なのか
- 記述力をどの程度求めているか
これらが見えてきます。
2. 時間配分の感覚を身につける
- 各大問にどのくらい時間をかけるべきか
- 見直しの時間はどの程度確保できるか
- 難問に時間をかけすぎず、時には飛ばすことができるか
実際の試験時間で解くことで、本番での時間感覚が養われます。
3. 自分の弱点・得意分野の発見
- 計算ミスが多いのか、思考力が不足しているのか
- どの単元が苦手なのか
- 逆にどこで確実に点を取れるのか
これを知ることで、残り数ヶ月の学習計画を立てやすくなります。
4. 出題形式に慣れる
- 問題用紙の構成
- 解答用紙の書き方
- 選択肢の傾向
- 記述問題の字数制限など
学校によって全然違うので、慣れておくことで本番での戸惑いを減らせます。
5.自信とモチベーションの向上
- 解ける問題が増えることで自信がつく
- 志望校への具体的なイメージが湧く
- 勉強の方向性が明確になる
といったメンタル面でのフックにするため。
以上が過去問に取り組むべき理由、でした。
過去問をやるべき理由を理解した上で、じゃあわが子はどのように進めていけばいいのか、どんなふうに考えていけばいいのか、を順番にお伝えしていきますね。
全部で9項目あります。長くなりましたので、二つに分けて書きますね。
1. 何年分やればいいの?
これ、すごくよく聞かれるんですが、
一般的には、第一志望校:5年〜8年分 、第二・第三志望校:3年〜5年分、 前受け校お守り校:1年〜2年分くらいといわれています。
複数回受験がある学校なら、回数で考えていけばよいと思いますが、
ここで注意してほしいことが2つあります。
注意点1:学校の傾向を見極める
まず、その学校が「出題傾向があまり変わらない学校」なのか、「傾向をつかみにくい学校」なのかを見極めること。
一般的には前者は伝統校に、後者は最近共学化した学校など新興校に多いです。
もし後者の傾向をつかみにくい学校だったら、10年分もやってもあまり意味がないですよね。対策がたてやすい学校なのか、たてにくい学校なのか迷ったら、塾の先生に聞いてみるのが一番です。
もしくは、高偏差値で人気校にもかかわらず早稲田アカデミーのNNやSAPIXのSSで冠特訓が作られていない、作られていても少ない学校…例えば渋渋などは、対策が立てづらいんだろうな、と思っていただいても良いと思います。
注意点2:社会は特別
社会は時事問題や生産量のデータなどが年度によって変わるので、あまりたくさんの年度をやらなくても大丈夫です。
その分の時間は、時事問題の学習などにあてた方がいいかなって思っています。
時事問題は、秋以降に出版される時事問題集を1冊購入して、パラパラ見ておけばよいと思います。
時事問題集、色々あって選べない!という方は、通っている塾が出しているものを購入されたら良いと思います。
早々に取り掛かりたい!という方は、こちらが一番最初に発売されますので、購入されるとよいと思います。
2. どの学校から手をつける?
2つ目は、複数ある受験校のうち、どの学校から手を付ければよいか。
基本的には、志望度が低い学校のほうが、難易度は下がると思いますので、そこから始めるのが良いのかな、と思います。
ただ、第1志望を直前まで全く解かないというのは避けたいので、うまくまぜながら、だけど「固め打ち」できるようなスケジュールを立てるのがおすすめです。
毎回毎回違う学校をやると、それぞれの学校の傾向や特徴をつかみにくいんです。
例えば、
【9月】前受け校やお守り校2年分+第1志望校 1年分
【10月】第3志望校4年分 + 第2志望校 1年分
【11月】第2志望校4年分 + 第1志望校 1年分
【12月】第1志望校4年分
【1月】今までの復習 + 第1志望校の最新年度含む2年分
こんな感じで、同じ学校を連続してやることで、その学校の「クセ」みたいなものが見えてくるんです。
3. 新しい年度から?古い年度から?
これ、私も最初は迷いました。
今までは、「最新年度は最後に残して、新しいものから古い方へさかのぼる」って考えていたんです。
でも最近は、「新しいものをまず解く、もしくは少なくとも見ておいた方がいい」って考えるようになりました。
なぜかっていうと…
例えば、最新年度を1月の最後の最後まで残しておいたとしますよね。 1月にそれを解いた時、今まではあまり出ていなかった立体切断の問題が出たとします。
そこから「あ、立体切断やらなきゃ!」って対策するのは、かなり厳しいですよね。
だったら9月の時点で、前もって最新年度を解く、もしくは見ていたら、「あ、この学校、って立体切断でるんだ」ってことで、そこから3ヶ月、4ヶ月かけて立体切断の対策を取れます。
だから少なくとも9月に入ったら、各学校の最新年度には目を通しておくことをおすすめします。
4. どこで手に入れる?!
ではその過去問を、どこで手に入れればいいのかを優先度が高いほうからお伝えしていきます。
1. 学校で入試問題そのものを販売している場合
まず、一番は、学校で現物を販売あるいは配布している場合は、そちらを手に入れてください。
説明会で配られる、文化祭で販売している、郵送してくれる・・・色々なパターンがありますので、志望校のHPでチェックしてみてください。
私が買ったことがあるのは、慶應湘南藤沢中等部(SFC)や栄光学園です。
一つ注意点があります。この原本を手に入れた場合、解答や解説はついていないことがほとんどです。そのため、過去問題集を購入するなどして別で手に入れる必要があります。
2. HPに過去問を載せている学校
原物を紙で配布していない場合は、データがHPに載っていないかチェックしてみてください。
例えば女子校なら大妻・東洋英和・品川女子・普連土・実践女子・光塩・山脇など
男子校なら海城・本郷・早稲田・獨協・鎌倉学園・東京都市大附属など
探せば結構あります。
このうち東京都市大附属は解答はもちろん出題の狙いや、全受験生と合格者それぞれの正答率まで公開してくれているので、受験予定の方は必見です。
3. 四谷大塚の過去問データベース
次に、四谷大塚の過去問データベースを見てみましょう。
主要な学校の入試をスキャンしたものがデータとして載っています。
四谷大塚に通っていなくても、会員登録さえすれば、誰でも無料で閲覧可能です。
ただ国語は著作権の観点から、載っていないことが多いです。
今までお話ししてきた、3つの入手方法は、原本、もしくは原本をスキャンしたものになりますので、配置や余白の感じも入試と同じものです。
なぜ出版社がだしている過去問題集よりこちらを優先するのかというと、より本番に近い状態で練習できるからです。
例えば武蔵の算数の問題を見てみてください。
40年以上変わらず手書きになっています。
ずっと市販の過去問題集をやっていて、本番で「えっ、手書きなんだ!」と動揺しないためにも、まずはこちらのデータベースに載っていないか、チェックしてみましょう!
ちなみに余談ですが、武蔵の算数は例年大問が4題。4人の先生が書いていて、それぞれ筆跡が違いますが、武蔵生が見れば誰が出題者か一目瞭然だそうです。面白いですよね!
4. 最後に声の教育社をコピー
ここまでの方法でなかったら、市販の過去問題集の最新年度を購入してください。
アマゾンやメルカリで探すと、去年のものも売っていたりするのでご注意ください。特に春に早々と買っておこうと意気込んでいると、去年のものだったりすることもありますので、お気を付けください。
過去問の印刷について、推奨はB4やA3用紙なので、ほとんどのお家では、今まで使っていた家庭用プリンターでは対応できません。
そのため、秋以降コピー機の購入を検討する家庭が多いのですが、コピー機は4万円前後からたかいものですと10万円くらいのものまでピンキリです。
大きいし、そこそこお値段するので失敗したくないですよね。
コピー機のおすすめは、別記事にまとめているので、よかったらそちらも見てみてくださいね。

入試期間中だけしか使わないなら、業務用コピー機をレンタルする方法もあります。その場合、故障した場合や、トナーの交換などは業者がやってくれ、また指定すれば冊子状にして、本番さながらの状態にコピーしてくれるので、場所はかなり取りますが、最近ではこちらを利用している方も増えている印象です。
とにかく、絶対に原本には書き込まないでください! 何度も解き直しができるように、コピーは必須です。
5. どこの出版社の過去問がいい?
首都圏の学校別であれば、声の教育社が主流です。
前にインスタでアンケートを取ったことがあるのですが、9割近くの方が声の教育社と答えてくださいました。
解説も詳しく載っています。
ここで知っておいていただきたいことは、配点は各出版社想定の学校が多いということですまた、回答が出版社によって異なることもありますので、特に国語でン?と思ったら塾の先生に聞いてみましょう!
過去問はほかにも、「有名中」と呼ばれる声の教育社の「有名中学入試問題集」や、「銀本」と呼ばれる「中学入試試験問題集」というものがあります。どちらも学校別ではなく、色々な学校の入試問題が載っています。
その分お値段もお高め。有名中は1冊6000円くらい、銀本は科目別なのですが、1科目3000円前後です。
かなり分厚くてこれが、コピーしずらい!そのため皆さん、裁断してコピーされています。
ノリのところを柔らかくするために、電子レンジに入れる、とか背表紙にアイロンを充てる…などを裏技をフォロワ-さんから教えていただきましたが、おすすめしているわけではありません。自己責任でお願いします。
銀本は色々な学校の問題を見ることができる、という点で優れていますが、解説がないため、学校別の過去問と併用してください。
全部の学校が乗っているから銀本だけで済ませる、ということは難しいと思います。
使い方としては、過去問題集を買うまでではないけれど、どんな問題を出すのか見ておきたいときや、学校を横断して問題を解きたいとき。
例えば、社会の地理で、雨温図の問題が苦手、志望校の過去問や模試でいつも間違える、という時に、受ける受けないに関わらず、雨温図の問題を探して解く、そんな風につかえます。
6、いつから、どのタイミングでやる?
過去問を始める時期は一般的には夏期講習が終わったちょうどいまくらいのタイミングです。
ただこれも、推奨の開始時期は塾によっても色々です。
夏休み前から、ちょこちょこ始めている塾もあれば、「10月になるまでやらないでください」という塾もあります。
カリキュラムの進度との兼ね合いだと思いますが、その場合は国語でしたら、そこまで影響がないと思いますので、国語から始めてみるのもてですね。
そして多くのママがこの時期に過去問を解く、と聞いて思うこと。
「今解いても太刀打ちできないんじゃないかしら・・」
そうなんです。この時期やっても、おそらく玉砕します。
でもそれでいいんです。前編でお伝えした、過去問を解く意味を思い出してください。
この時期過去問を解く意味は、志望校の傾向や相性を見るためであって、合格点が取れるかどうかを見るためではないからです。
だから、点数で一喜一憂するようなお子さんには、「最初は点数取れないけど、それで大丈夫だからね。どんな傾向の問題が出るのか知るためと、入試に慣れるためにやるんだから」って、伝えておいてもいいですね。
ちなみに我が家の話ですが、長男は秋に受けた「志望校別のオープンテスト」の算数で、120点満点で12点をたたき出しました。それでも本番では合格できましたので、あきらめるのはまだ早いです!
全然点数が取れなくて、「え、無理じゃん」とやる気をなくすことだけは避けたいですよね。
7、4教科まとめてやる?
過去問をやる、というと、「4教科まとめて入試本番さながらにやる」のをイメージしている方も多いかもしれません。
ですが、実は4教科通してやれる日は想像しているよりも少ないです。
1月に小学校をどのくらいお休みするのかにもよりますが、4教科通しでできる日は本当に限られます。
試しに、2025年度、9月から2月1日まで、週末が何回あるのかかぞえてみたところ、21回。
仮にこの週末が全部使えたとしても
第一志望校8年分
第2志望校5年分
第3志望校5年分
前受け校、お守り校3年度分
ができる回数です。
ですが、関西や帰国生入試ではもっと早くから入試が始まりますし、秋からは週末に模試もあったり、土特日特のような特別講習が組まれている塾も多いです。それに加えて秋は運動会や修学旅行など、小学校でもイベントがたくさん。
もうお分かりだと思います!通しでやれる時間・・・、本当に少ないです。
そのため、塾のない日に1教科、4教科通しでできそうな日は、第一志望校をやる、など工夫が必要です。
このスケジュールは、お子さんには難しいと思います。ぜひ親御さんがやってあげてください。パズルみたいで、意外とたのしいですよ!こういうのが得意なお父さんも多いので、思い切って任せるのも手です!
ただ、ここで気を付けたいのは、ぎちぎちに詰めすぎないこと。相手はロボットではありません。
10才11才の子供です。体調を崩すことだってあるし、疲れて「今日は無理~」っていう日もあると思います。
運動会の次の日曜日はあえて開けておく。模試の後の午後は、2教科にするなど少し余白を残し、「できたらラッキーくらい」の気もちでいると、狂気が出ずにすみます。
8、何周もする必要ある?間違い直しは?
非常に残念なお知らせではありますが、間違い直しはしたほうが良いです。
「過去問をやる意味」にもありました。苦手単元や苦手問題の洗い出し・・・。
苦手がわかっただけで対策しなければ・・・、意味がなくなってしまいます。
ですが、わかります。子供たち・・、解きなおし嫌いですよね~
そこで、優先順位をつけてやっていきましょう。
まずは何はともあれ算数の見直しです。間違えた問題で、
①計算ミスなど本当なら解けた問題
②時間がなくて解けなかった問題
③解説を見たら理解できた問題
は復習しておきましょう。
解説を見てもさっぱりわからない・・・、そんな問題はいったんスルーしてよいと思います。
もしできたら、解説を見て理解できた問題は、間違い直しノートを作るといいと思います。
この時ノートではなく、ルーズリーフでやるのがおすすめ。
単元ごとに入れ替えることができますし、何度も解いて完全に解けるようになったら、ファイルからはずしてしまえます。
次に国語です。
国語はまず漢字や語彙で間違えたものを、こちらは1冊のノートにしておくのがおすすめ。
算数のファイルは挫折した我が家ですが、この国語の間違いノートは「ママ漢」と称して、3人とも作っていました。入試にも持っていった子どもたちのお守りノートになっています。
作り方はインスタで詳しく説明しています。
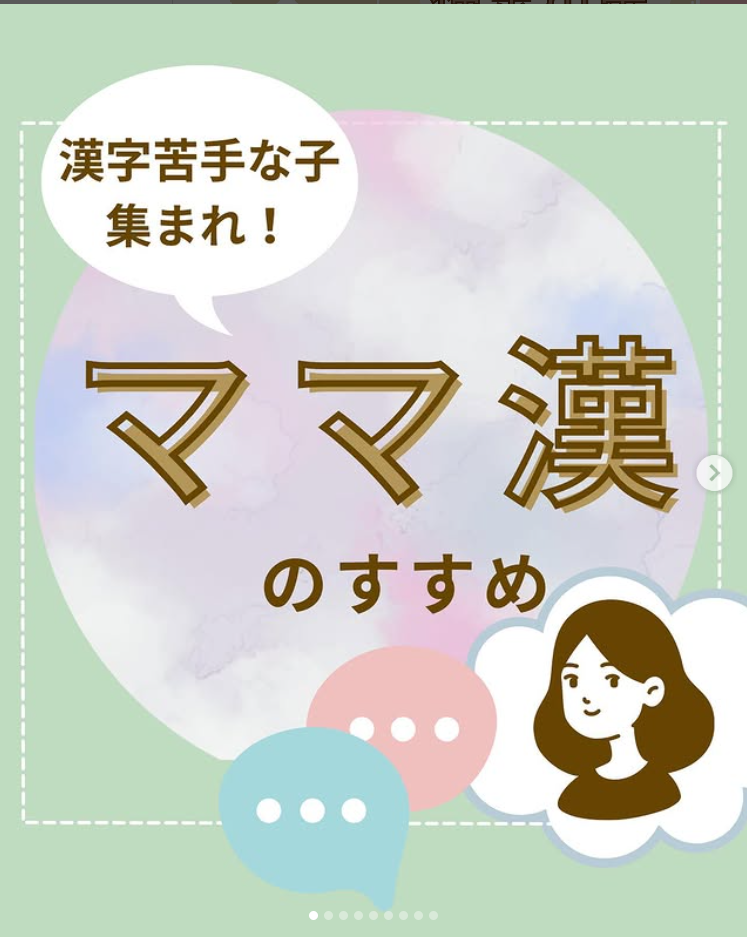
読解問題は・・・、すごく言いにくいのですが、ここは親御さんがある程度関わらないと、こどもだけでは難しいと思います。
大部分の子供が、答えをみて「あ~、そっちね、はいはい」という感じで、なぜ間違えたのか?どうしてその選択肢になるのか、など深堀りすることは難しいからです。
親御さんがそこまで関わるのは難しい!という場合は、個別塾や、家庭教師に頼るのもアリだと思います。
次に理科と社会は、まず暗記物は、知識項目を整理して、視覚的にわかりやすくまとめて、リビングやトイレに貼っておくといいです。
わざわざ暗記する時間を作ることは難しいので、こんな風にすき間時間を利用しましょう!
その時のちょっとしたコツです。
例えば、夏の大三角のこと座のベガを間違えたとしましょう。
その時にこと座→ベガと書くのではなく、周辺知識をまるっと復習できるように書きましょう!
夏の大三角こと座のベガ、わし座のアルタイル、白鳥座のデネブ、
もう一つ夏を代表する星座はさそり座、その1等星はアンタレス。アンタレスの色は赤。
冬の大三角もいっしょに・・・。みたいな感じです。
解きなおしをしていれば、個人的には何周もする必要はないと思います。それよりも、まだ解いたことのない年度に手を付ける方が、得られるものは多い気がしています。
9、 〇付けは誰がする?!
まる付けは基本親がやってあげましょう。
子供がやると、精度が落ちたり、丸付けをしている最中、解答を見る機会があるわけなので、見ようと思っていなくても、ほかの年度の回答が目に入ったりしてしまうからです。
国語の記述など、親が判断に苦しむようなときは塾の先生にお願いしても良いと思います。
ただ多くの場合、すぐには帰ってこず、2週間くらいかかったりするので、手元に来る頃には、これってなんだっけ?となる可能性もあります。
秋から家庭教師の需要が増えるのも、この過去問対策であることが多いのもうなづけます。
うちの塾、添削してくれるかしら?と思ったママのために、フォロワーさんに、「添削してくれる塾アンケート」も取っています、こちらはYOUTUBEの概要欄に受け取り方法を記載しましたので、ご覧ください。
丸付けが終わったら、点数を一覧で管理できる表を作っておくのもいいと思います。
過去問をやりすすめるうちにだんだん、どこの学校の何年度分の何の科目をやったのか、訳が分からなくなってきます。
一目で、学校別の進捗がわかるもの、またお子さんの点数と、合格最低点を比較できるものがあるとすごく便利です!
皆さん、お忙しいと思いましたので、こちらも私がスプレッドシートで作りました。
こちらもYOUTUBEの概要欄に受け取り方法が書いてあります!
最後に
いかがだったでしょうか?
過去問って、取り組み方一つで効果が全然変わってくるんです。 でも一番大切なのは、お子さんの状況をよく見て、柔軟に対応すること。
「みんながやってるから」じゃなくて、「うちの子にはどの方法が合うかな?」って考えてみてくださいね。
もちろん、全部を完璧にやろうとしなくても大丈夫。 できるところから、無理なく始めていきましょう。
私は現在中学受験ママのためのコミュニティを運営しています。
何かわからないことや、相談したいことがありましたら、いつでもお寄せください。